
書誌情報
- 出版社
- 集英社
- 最大 No.
- 3073
感想
本書の書名となっている『エンジェルフライト』は、有る会社の車に書かれたロゴのような存在を文字に落とし込んでいる。なんだか幸せを運んできそうだが、業務内容は副題となっている「国際霊柩送還士」である。
漢字で書かれれば、多くの人はあまり関わりになりたくない、と思う人が多いだろう。実際にはどのような業務なのか? 巻末の解説によると
海外で亡くなった邦人を日本へ搬送するプロフェッショナル。彼らは「国際霊柩送還士」と呼ばれるそうだ。
2975
国境を越えた遺体の搬送には実に細かな作業が必要とされるが、その代表的なものがエンバーミングと呼ばれる遺体の腐敗防止処置だ。血管の中に防腐剤を注射で流し込んで全身に行き渡らせた上で、体液が漏れないように穴を 1 つ 1 つふさぐなど細かな作業をしていかなければならない。
2983
やはり、できれば関わりたくないと思う人が多いとは思う。しかしながら
遺族は異境の地で家族が死亡したことを認められないし、認めたくない。だから遺族には、その死を受け入れる儀式が必要なのだ。遺族が柩に納められた故人と対面し、頰をさすって何度呼びかけても返答がないことを知り、やがてせめて天国へきちんと送り出してあげようという覚悟を決める。それが身内の死を受け入れるということなのである。
3008
遺族にとって国際霊柩送還士は、悲しい思い出に寄り添う人々である。だからこそ、彼らは丁寧な仕事に感謝しながらも、その記憶を消していこうとする。実際、エアハース・インターナショナル社に遺体の搬送をしてもらった遺族の中には、同社によって支えられたという記憶はあっても、利惠たちの顔や言葉の記憶がなくなっている者もいたという。
佐々はこれについて次のように言う。「ああ、これでいいのだ」
そう、遺族にとってはこれでいいのだ。
だが、社会として国際霊柩送還士の存在が薄れていいわけではない。遺族には忘れ去られても、社会的にはきちんとその重要性が記録され、認知されるべきなのだ。特に今後グローバル化が進めばさらに重要な存在になることは間違いない。
3034
の通り、世の中に必ず必要とされる業務なのだ。
人は不死では居られない。そして、どこで死ぬかの選択が出来るとは限らないのだから。
本書はその世界を描いたルポである。
縁遠い世界。できれば関わりたくない人が多いとは思うが、多くの人に知ってほしい世界。そんな本。
現在は、多くの人が親族を病院で看取り、死を遠ざけている。重ねて書くが、人は不死では居られない、にも拘わらず。
今後国の財政上の理由や、医療資源の有効利用の観点から、在宅での看取りが増えていくと思われる昨今、避けられない人の死を、直ぐ身近に有るものと思い起こさせる意味でも、手にとって読んで欲しい。
印象的な箇所
同じ時期に、この地域からずさんな処置をされた日本人の遺体がもう一体戻っている。そこで搬送の履歴をたどると、どうやら同じ業者が絡んでいるらしい。その街ではたちの悪い連中が救急病院を徘徊しており、死者が出ると、有無を言わせず知り合いの葬儀社に運んでしまうという。一度手元に置いてしまえば、高額の遺体保管料金が発生する。彼らはいわゆる「遺体ブローカー」なのだ。遺族に業者の優劣などわかるはずがない。これから遺体にどんなことをされるか (あるいはされないままで放っておかれるか) 事情を知らないまま、遺族はエンバーミングを委託してしまうのである。
63
無知だと食い物にされう典型。
我が国では近年プライバシーへの配慮が進み、死は究極のプライバシーとして人の目から遠ざけられることとなった。それは同時に、正しい知識や判断力を我々から奪う。日本で亡くなった外国人の遺体は、どこでどんな扱いをされているのか、私たちにはわからない。それどころか、外国人が日本で死ぬということすら考えたこともない人が多数なのではないだろうか。人が生活しているところには死があるという事実を、長い間日本人は考えずに暮らしてきた。
希釈された死は、テレビドラマにも映画にも溢れているが、虚構の世界に死の真実はない。代替品を消費しているに過ぎないのだ。本当の死を目にしない不自然な世界を作り上げ、我々は長い間そこに籠って死から目をそむけてきた。
しかし、死のあり方は、見えないところで、時代とともに変わっている。
233
依頼は、大きくふたつのケースに分けられる。保険ケースとプライベートケースだ。海外で亡くなった人が、海外旅行傷害保険に加入していたり、海外旅行傷害保険付きのクレジットカードを所有している、あるいは勤務先がアシスタンス会社と契約している場合には、アシスタンス会社は保険で国際霊柩送還を請け負う。そしてそのアシスタンス会社が遺体搬送業務をエアハースに依頼するのである。
保険に入っておらず、個人で遺体を連れて帰りたいと思っている人々からも、エアハースに連絡が来ることがある。それについてエアハースではプライベートケースとして対応している。
もちろん遺族が自ら手続きをしてもいいのだが、不可能とは言わないまでも、かなり難しいようだ。中でも難しいのは、遺体が国境を越える際の手続きだ。
日本では想像しがたいが、悪質な業者が、棺の中に武器や麻薬を入れて運ぶこともあるだろうし、遺体と一緒にそれらの禁制品を忍ばせて密輸することも考えられる。海外に潜伏している犯罪者やテロリストが、身代わりの遺体を棺に詰めて本国へ送り出し、死んだことにして逃げおおせる、などということもあるかもしれない。また、伝染病で亡くなったものではないという証明も必要だ。これらのことを踏まえると、手続きにはさまざまな証明書を揃えなければならないことがわかる。しかも、書類は国によって異なってくるし、手続きの際に使用される言語もさまざまだ。
傷害保険に加入していない場合、遺族にかかる負担は決して小さくない。実情を知れば、保険に入らずに海外旅行に行くことが、いかにリスクが高いか理解できるはずだ。
975
アメリカではエンバーマーはライセンス制だ。アメリカのエンバーミングの水準は高く、各国と比較して最もいい状態で帰ってくる。アメリカでエンバーミングが広く普及することになったのは、南北戦争の頃 (1860 年代) で、死者を搬送する必要があることから一般的になった。アメリカは国土が広いため、遺体を搬送するだけでなく参列者が葬儀に到着するまでにも時間がかかり、さらにほとんどが土葬されるという埋葬事情から、伝染病の蔓延を防ぐために 90 % 以上の遺体にエンバーミングが施されている。
1006
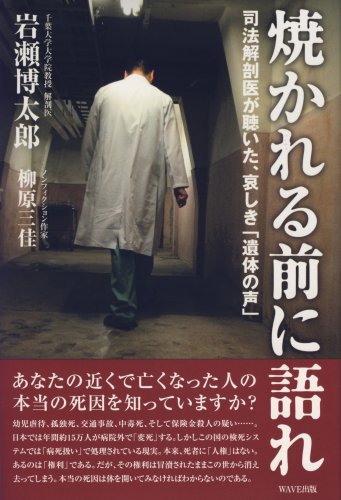
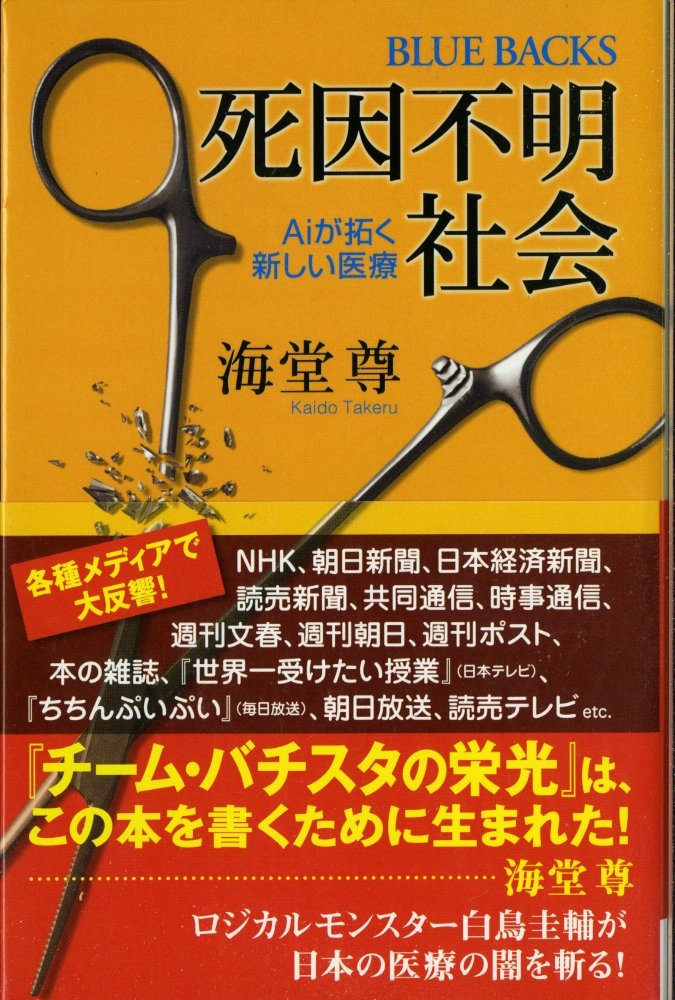
日本は正しい死因救命が行われていないことといい、死を遠ざけるが故に、死を軽んじているのかも知れない。
一部アジア地域の遺体の保存状態の悪さについては、遺体に対する考え方や文化的な違いからではないか、というのは現場で働いている人たちの感想である。
1015
家族にとって遺体を故郷に連れ帰りたいという願いは切なるものなのだ。今の日本で、死後の世界について問えば、魂の存在を信じていると言いきる人は少ないだろうし、生まれ変わりや神の存在についても肯定する人はそう多くないだろう。だが、はたして私たちは本当にそう思っているのだろうか。
遺族を見ていると、私たち日本人の多くがそれほどドライではないことに気付く。
もし家族のひとりが異国で命を落としたら、遺体がどんな状態であってもかまわない、一部分であってもいい、戻ってきてほしいと願うのではないか。亡くなった人が異国で「さびしがっている」と思い、日本に「帰りたがっている」と感じるに違いない。
人々は、死後の世界などはないと口では言いながらも、亡くなった人の心は亡くなったあともまだ存在しているとどこかで信じているのだ。身内の死を前にすれば、日頃漠然と考えている「死」はただの抽象概念でしかなく、頭で日頃思っていた「死」とかけ離れていることに気づくのだ。葬送は、理屈では割り切れない遺族の想いに応えるために存在している
1042
非合理な儀式をあえて行うことで、遺された者は死者を彼岸へと送り出す心の整理をつけていくのだ。「死」は家族だけで対処しきれるものではない。今まで一緒に生きてきた家族を別の世界へ送るには、愛着が強すぎるからだ。家族はいつまでも亡き人の死を受け入れがたく、現世にそのまま引きとめておきたいと願う。場合によっては死の国へ一緒に行きたいと願うのである。
それを葬儀によって彼岸へ送り出す。非日常的な葬送の儀礼は目に見える形でこの世とあの世の通路を作る行為である。そこでは僧侶、親族、葬儀業者、地域共同体の、目に見えない慰霊の力、祭礼を行う力が試されている。それはもちろん金額に換算できるものでも、合理的な説明がつくものでもない。
1261
団体の広報担当者はこのようなことを言ったのである。「現地では政情不安が続いており、いろいろな勢力がいろいろな考えを持って動いている。
あなたがもし彼を英雄視していると思われるような記事を書くと、我々の活動を快く思わない勢力によって、現在現地で働いている職員の命が脅かされる恐れがある。エアハースのことは我々もよく覚えているし、ご遺族も大変喜んでいらっしゃった。
でも、今はインターネットも発達し、日本で彼のことを讃えるような報道が出ると、すぐにこちらで不穏な動きがある。代表も命を狙われている。先日も警察官がやってきてあれこれと注意を受けたぐらいだ。彼の遺志を継ぐためにも、現地が一日も早く復興できるように我々が安全に支援できることが第一だ。どうか、報道を控えていただきたい」
1414
親を失うと過去を失う。
配偶者を失うと現在を失う。
子を失うと未来を失う。
1640
全国霊柩自動車協会によると、2011 年 3 月の震災発生直後から 5 月末までのピーク時には岩手・宮城・福島・東京 (都と被災県との協定による搬送) の 4 自治体に 190 事業者から延べ 940 台が出動、1500 体以上の遺体を運んでいる。このうち岩手、宮城両県ではほとんどが「ボランティア」として稼働。規定の運賃、料金とはほど遠い報酬で過酷な遺体搬送に従事していた (物流ウィークリー「遺体搬送はボランティアか 規定運賃とほど遠い報酬」より)。
そのことに関して苦情は一件も寄せられていないという。どの業者も少しでも役に立ちたいという心情で集まってきたのだ。しかし、きっとまた近いうちに災害による死者は出るだろう。その時どうするのか、どう運ぶのか。今から考えておくべきことはまだまだあると山科は思っている。
1698
入社して間もない頃は遺体を運んで遺族と顔を合わせるのが怖かった。遺体と対面するなんて、遺族にとってこれほどつらいことはないだろうと思ったからだ。
だが遺族は決まって喜んでくれた。「あんなに遠い国から、私たちのもとに帰してもらって、本当にありがとう」と言う人もいれば、「眠っているように見える。穏やかな顔で帰してくれてありがとう」と言う人もいる。だが、どちらにしても遺族の口から聞こえてくる言葉は、恨みごとではなく感謝の言葉なのだった。
遺体を家族のもとに届けることは、これほどまでに遺族の気持ちを慰めることなのかと送り届けるたびに実感した。もしかしたら、霊柩業務なんてと世間では眉をひそめるかもしれない。だが、こういうふうに人の役に立っている。無事に遺体を家族のもとに届けることが、自分たちにとっての誇りだった。最近昔の友人から、顔が柔和になったとよく言われる。きっと人に感謝される仕事をしているからなのだろう、と古箭は思っている。
しかし、もちろん遺族は愛する人を永遠に亡くしたのだ。そう思うと、古箭は一層切ない気持ちになった。
1820
いろいろなご遺体を運ぶでしょう? 自然死の場合には、ご遺体と対面して笑顔になる人もいるんですよ。でも、自殺は空気がたまらなく重い。名前を叫んで家族が足をさすっている場面も見ました。『どうして? どうして?』と何度も問いかけている場面も見ました」
そう言いながら、古箭の目は潤む。
だが、たとえ遺族にとってどれほどつらい対面であっても、遺体を日本の家族のもとへ帰すこと、そして日本できちんとお別れをすることは何より大事なのだと古箭は考えている。「人って区切りをつけることが必要なんですよ。海外で故人を送るのと日本で送るのじゃやっぱり違う。きちんとしてやれた、と思えることが、これほどの苦しみの中でもほんの少しの救いになるんです。葬式なんて普段は必要ないと思うでしょう? でもね、そういう現場をいくつも見ていると思います。ああ、やっぱり必要なんだなって。そして、きちんと葬式をしてやれたってことは大事なんだなって。あんなにつらい目に遭っている人がすごく感謝してくれるんですよ。ありがとう、ありがとうってね」
1857
自殺の時についた首の傷に、海外で防腐液を入れるために鎖骨の辺りと足の付け根についた傷、そして解剖痕。それがたまらなく痛ましかった。
親にもらった体に傷をつけちゃいけない、なんて古い考えだと思っていたが、やはりそれは正しい、と思う。
1873
高速に乗っていると、なにげなく見た景色の中に真冬の富士山がくっきりと見えたのである。
若い頃、新聞を毎日のように輸送して見ていたなじみのある山である。その姿があまりに鮮やかだったので、彼は若い頃のことや、自分の母親のこと、自殺した先輩のことなど、いろいろなことを思い出した。
古箭はその時、「あ……」と思った。
自殺したあのお兄ちゃんは、それでも日本に帰ってきたんだよなあ。
それでも、自分の国、日本で荼毘に付されたんだよなあ。
そう思った瞬間、古箭の両の目からぼろぼろと涙がこぼれた。
なぜか、泣けて、泣けてしかたがなかった。
日本人だなんて意識することは普段ないのに、どうして死の現場では日本を想うのだろう。どうしてこれほどまでに日本の景色は美しいのだろう。
あのお兄ちゃん、日本に帰れてよかったなあ。
富士山は雲ひとつない空に、真っ白い雪をたたえて美しい稜線を描いていた。古箭はこの光景を 2 度と忘れないだろうと思った。
1897
エアハースの行っている遺体搬送は、悲嘆に遺族を向き合わせる行為だ。弔いは亡き人を甦らせたりしない。悲しみを小さくしたりもしない。かえってとり返しのつかない喪失に気づかせ、悲しみを深くするかもしれない。
だが、悲しみぬかなければ悲嘆はその人を捉えていつまでも放さない。私は心のどこかで知っていたのだと思う。国際霊柩送還とは人を悲嘆に向き合わせることにより、人を救う仕事なのだ。
1956
私たちはある日、医師に別室に呼ばれて「胃ろう」を作るか否かを問われた。
胃ろうとは栄養チューブを通すために胃にあける小さな穴だ。胃ろうについては批判もあり、不自然な延命だとする意見も多い。
医師はその時、こんなことを言った。「尊厳死などと言いますが胃ろうを作らないということはつまり餓死させることです。お母さんはお若いですし、体もしっかりしている。餓死するまでは何週間もかかるでしょう。スタッフもご家族もそれを見ているのは非常につらいことだと僕は思います。鼻から栄養を入れる方法もありますが、鼻から液体を入れることを想像してみてください。あなたもつらいでしょう?
実際に胃ろうを作らないと頑張っていても、そのうち見ていられなくなり、患者さんの体力が落ちてから、あわてて胃ろうを作ろうとするご家族もいらっしゃいます。でも弱った体に胃ろうの手術をすると思わぬ事故が起きることも多い。ご本人にとっても負担です。あとはご家族のご意向次第です。みなさんで決めてください」
母がこうなるまで、私は疑いようもなく尊厳死に賛成だった。文化人も良識のある医師もみんな尊厳死について積極的に「いいことだ」と勧めている。逆に食べられない人に体が不自由なまま生きていてほしいと望むことは家族のエゴだと批判されていた。私も新聞でそんな記事を読みながら、さしたる考えもなく、その通りだと思っていた。
尊厳死は人道的な行為。それに反対しているのはヒステリックな患者の家族の会。そんな構図が単純に頭の中にあった。母も「お父さんにお世話されてまで生きているのは嫌だわ」と言っていたはずだ。私もそう聞いたのを覚えているし、父だって、母だってその時のことを覚えているだろう。
だが実際に、生きている体を前にして、書物で読んだ「死」と大きくイメージが違うことに戸惑った。温かい体がそこにあり、何が起きているかをすべて理解している瞳が様々なことを訴えてくる。ただいてくれることが当たり前の静かな日々を私は失いたくなかった。この人が私のたったひとりの母だ。そこに失くしてしまっていいものなどを私は見つけられなかった。簡単に命を救えるのにあえて不作為を選択する理由が私にはどうしてもわからなくなっていた。家族は胃ろうを選択し、父が実家で母を看ることになった。
2246
本書で、違和感を抱いた数少ない箇所。そもそも胃ろうをするか否かで、医師がここまで踏み込んで、勧めて良いのか? 本人が望むならともかく、その本人の意志が解らないのに。しかも医療資源・財源は限られている。
死を扱っている人でさえ、実は近親者の死を想定していないのではないか?
改めて国際霊柩送還というものを考えてみると、不思議な行為だと思う。たとえ遺体の処置をしても、医療のように命を救うわけではないし、蘇生させるわけでもない。腐りやすい遺体を遠い国から運び、生きている時と同じ顔に修復してお別れをするのだ。次の日には骨にしてしまうのになぜわざわざ合理的とは思えない行為をするのだろう。科学の発達した世の中だ。生命の失われた体をただの物体だと済ませてしまうこともできるだろう。しかし我々はいくら科学が進歩しようとも、遺体に執着し続け、亡き人に対する想いを手放すことはない。その説明のつかない想いが、人間を人間たらしめる感情なのだ。私には、亡くなった人に愛着を抱く人間という生き物が愛しい。亡くなったのだからもうどこにもいない、と簡単に割り切れるほど、人は人をあきらめきれないのだ。
我々は亡くなった人の体に「魂」とも呼ぶべき、命の残響を聴いてしまうものなのである。ほとんどの人は、いざ親しい人の死に直面すると、「魂」がまだどこかにあると感じてしまうのではないだろうか。だからこそ懇ろに弔うことによって、「魂」を慰めるのだ。
2385
遺族にとって、利惠たちと出会ったのはまさに地獄に仏の心境だろう。だが、だからこそ、彼女たちの顔を思い出すと、胸を引き裂かれるような悲しみの記憶が甦ってきてしまう。
国際霊柩送還士たちにとって、亡くなった人と最も近い一日がある。それは遺体が帰ってきた日だ。彼らは処置をしながら懸命に声を聞き取ろうとする。その人の人生。その人の人柄。その人の伝えたかったこと。どんな姿で家族のもとへ帰りたいか。いつも、どんな髪型を好み、どんな笑顔をしていたか。そして家族に何を伝えたいか。
その一瞬、亡くなった人は利惠たちにとって、恋人よりも、家族よりも、ずっと近い人になる。アメリカではエンバーマーは神父や牧師の次に尊敬される職業であると聞く。しかしどれほど利惠たちの仕事が遺族の心を救ったとしても彼らのことを讃える声を聞くことはない。遺族は人生で一番つらい記憶を忘れようとするからだ。
無理もない。もし私が子どもを運んでもらったとしたらどうだろう。
私は利惠たちに、感謝して、感謝して、心の中で手を合わせ、きっと彼らを忘れるだろう。そして 2 度と思いだすことはない。
私は利惠たちに会ったことを忘れ、彼らの名前も顔も忘れ、子どもが亡くなったことすら忘れ、その子との幸せだった記憶だけを繰り返し、繰り返し、思い出す。最初に歩いた日のこと、最初に「ママ」と言った日のこと、抱きあげた時の髪のひなたのにおい、首に回した手の小ささ、泣きべそをかいて走っていた運動会のかけっこ、小学校の入学式、親子げんか。そして「行ってきます」と家を出たときの笑顔……。どんなにささやかな記憶でもそれをかき集め、寝る前にはひとつ、ひとつ、思い出す。
私はそう思うと、ふいに安堵の気持ちに襲われた。
ああ、これでいいのだ。
私は初めて国際霊柩送還士の本当の仕事を知ったような気がする。国際霊柩送還士は忘れられるべき人たちなのだ。裏方として彼らは一瞬、人の最もつらい現場に立ちあい、そしてまた裏方として人の目に触れない場所へと戻って行く。
2818
生きなさい。ふり返っていのちを無駄にしたと後悔しないように。
生きなさい。してきたことを悔やみ、別の生きかたを望むことのないように。
正直で、じゅうぶんな人生を生きなさい。
生きなさい。エリザベス・キューブラー・ロス
2818
東日本大震災の一年ほど前に島田裕巳著『葬式は、要らない』がベストセラーとなり、葬式不要論がブームとなった。家族や地域共同体の力が弱まり葬儀を維持できなくなったことや、昨今の葬儀の形骸化がその背景にはあるのだろう。
だが今震災を経験して、弔いというものが人間にとっては本質的に必要なのだと私たちは理屈を超えて気づきつつある。葬儀は悲嘆を入れるための「器」だ。自らの力では受け入れることができない悲嘆に向き合わせてくれるしくみなのだ。
2858