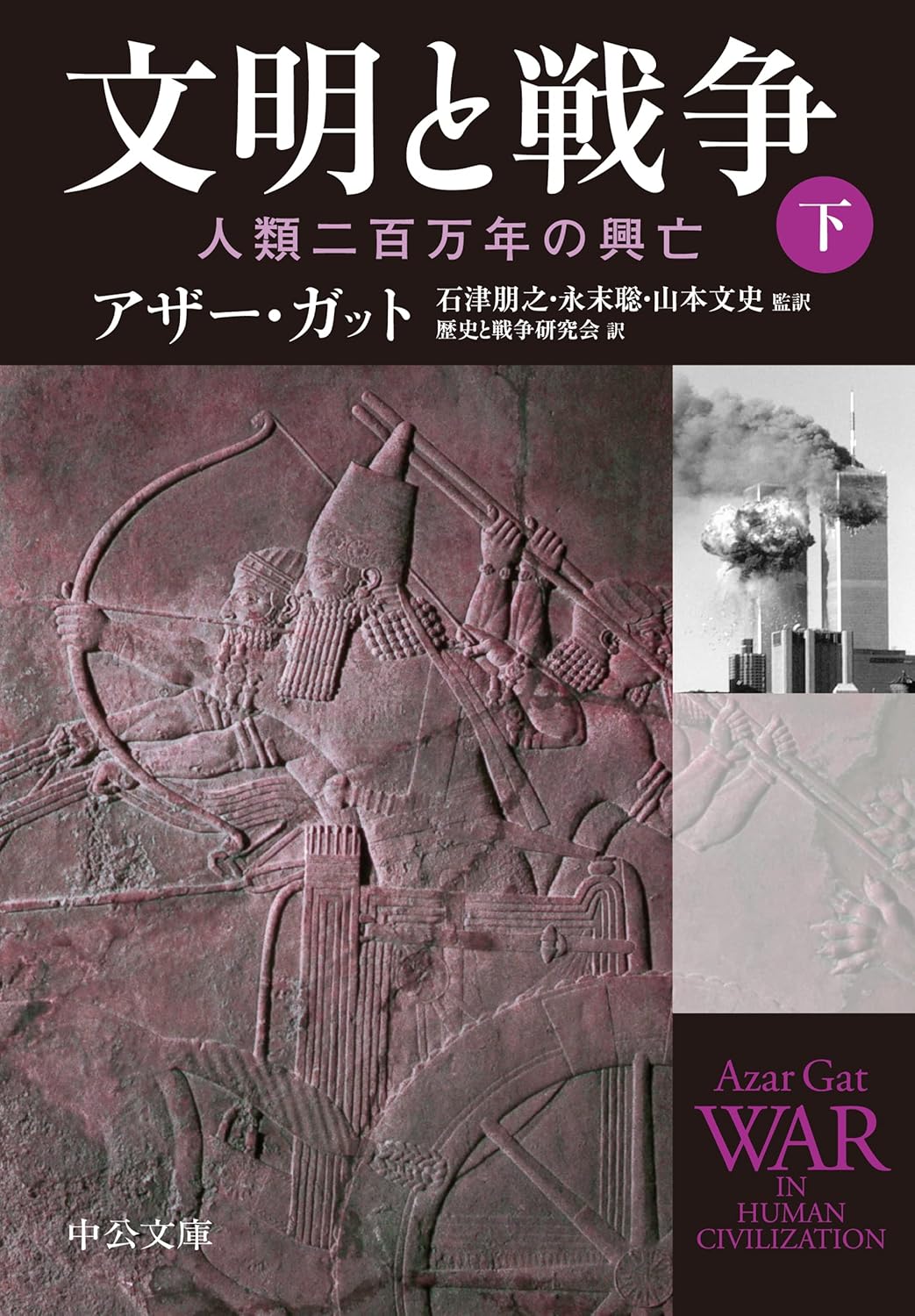記事
全体的に言えることとして、
- 先史時代は資料が少なく、どうしても、想像の範囲が大きくなってしまう
- 戦争というより紛争のほうがしっくりくるかも
- 文明より文化や、原題に基づいてヒト社会、「ヒトはなぜ戦うのか?」についての本? としたほうがしっくりする
- 全体的に説明が冗長で、くり返しが多い
- 数多くの事例を知ることはできるが、結論は出せないと感じ、納得できない結論もまた多い
- 都市の誕生が分業による結果ではなく、周りからの防衛だったということは、知らなかった
→この事を知ると、日本の町が、なぜ城壁で囲まれていないの? が不思議- 築城技術から考えても、発展段階の問題でもないし
- そもそも弥生時代には環濠集落があるし
- 上巻 p.35 辺りに、紛争などを含んだ殺人について狩猟採集民の争いについて、牧畜・農耕以後よりは、少ないと思っていたので意外…。狩猟採集民でそれ程多いとは。
- p.114 によると、嬰児殺しにより女児 100 に対する男児の割合が、
- エスキモー
- 150
- オーストラリアのアボリジニ
- 125
- アマゾンのヤノマミ
- 129
- アマゾンのシャバンテ
- 124
- ペルーのカンナワ
- 148
- フィジー
- 133
- モンテネグロ
- 160
- 仮説の部分も多く『戦争の世界史』の方がお勧め
以下、いつもの様に印象に残った箇所。
痩せザルやゴリラのオスは同様な行動をとることが観察されている。
26
この子供を殺す事については、マウンテン・ゴリラのタイタスが、別のオスの子を育てた例を知っていたので私には意外。
アボリジニは、長を他者に特段優越する存在として認めていたわけではなかった。しかし、集団全般にとりって最も熟練し、有能な存在である長は、そのことにより大いなる尊敬を集め、他者よりも多く妻を娶るに足ると考えられていた。
上 p.133
機会・理念平等であっても、結果平等ではないということか。
それは人問の他の動物とは最も違う能力である。道具を作るという能力のためである。能力がより発達すればするほど、人類はより死をもたらし得るようになり、同時に人間の肉体はほっそりしてくる。道具が筋肉や骨や歯の代わりになるからである。ホモ・サピエンス・サピエンスはネアンデルタール人やホモ・エレクトゥスよりも骨格がほっそりと出来ており、次第に大型類人猿よりも筋肉が少なくなっている。要するに、人間の攻撃能力の進化は、一貫した自然の防衛能力の低下とつながっている。
上 p.186
ヒトは攻撃力を持つほど防御カが落ちる、というのは考えたことが無かった。
では、なぜ世界の様々な地域の人々が、ほぽ同時に、突然、植物育成や動物の畜産に励むようになったのであろうか。学者はいまだにこの問題を議論している。以下は筆者が支持する総合的判断である、この動きの根本となった原動力は、おそらくは入口増加であった。
上 p.228
気候の安定化のほうが説得力を感じる。実際、そういったデータもあるし。
遊牧民が騎乗するのではなく、戦車に乗るようになった原因を説明しようと試みたアンソニーとヴィノグラドフは、次のように評価している。つまり、遊牧民が馬でなく戦車に乗るようになったのは、合成弓のように軌条の際に用いる効果的が武器が開発されていなかった結果であるかも知れないという。アンソニーとヴィノグラドフは、合成弓は紀元前 1500 年頃になってよくやく開発されたと主張している。しかしながら、第 - に、合成弓は彼らの主張する時期より、明らかに 1000 年古い時期に開発されていた。第二に、もし合成弓が存在しなかったことが事実であったととしても、その結果、戦車担当の戦士も十分に役割を果たすことができなかったはずである。第三に、騎兵隊は騎乗の際に、投げ槍や突き槍といった単純な弓を使用るることが可能であったであろう (実際、使用したと思われる)。
上 p.448 (補足部)
突き槍は鐙が登場して初めて効果を発揮するのではないだろうか。そうでないと踏ん張りが利かず、突撃した場合に落馬してしまう。
規模の拡大はこの全てに通底する基調であったが、暴力による死亡率は全般に、国家の成長と「戦い」から戦争への移行に伴って顕著に低下した。
下 p.113
文民の住民が戦闘にさらされにくくなり、また、成人男性の従軍率が低下したのである。こうして、軍隊や戦争、一回の交戦における死者は著しく増大した一方、国家間戦争がとりわけ破局的な絶頂に達する場合に限って、暴力による男性の死亡率が 25% に近づくこととなった。この比率は、小規模で細分化された社会では、絶え間ない集団内部および集団間での暴力のなかで当然に生じるものとして記録されている数値である。
下 p.114
この辺りの死亡率に関しての印象は、一般的な印象とは真逆だ。私も近代以後の方が戦死率が高いと思っていた。
しかし、仮に備砲要塞がそれ自体では以前の要塞より高価ではなかったとして、要塞に設置する大砲や備蓄する火薬や砲弾のおかげで、実際には新型要塞にかかる費用は、より高額になったのではないだろうか。どの国でも、大砲やその弾薬の大半は野戦軍よりは要塞に配備されていた。それでも、多くの研究者によって大砲は財政支出の大部分を占めると推定されているにもかかわらず、近世の様々な国家 (フランス. ヴェネツィア、スベイン、ロシアを含む) の個別データからは、大砲に関する支出が、ヨーロッパ各国の総軍事費に対して要塞が占めるのと同じくらい一貫して控え目な割合で、およそ 4% から 8% であったことが明らかになっている。携帯型の小火器も、非常に高価であった中世の防御用・攻撃用の鋼鉄製武器や弩と比べけた違いに高価なわけでもなかった。
下 p.188
銃火器への出費に関しては、ーつ一つの単価は以前とそれ程変わらなくとも、新規の兵器は、その力を十分発揮するには、兵全体の兵装を揃えなければならず、ー度の出費が多くなってくる影響は、如何程あったのだろう? (ただし、そうなるのは、後200年程後かな)
それ故、アメリカの自由主義的な体制がその巨大な成長のための前提条件であったとしても、アメリカか新世界の新しく発見された土地において出現し、最終的に「旧世界を敦う」ためにそこに存在したという事実は、少なくとも偶然性が働いた結果である。その巨大な力の集中は、20 世紀の間、それ以下の二つの大国を組み合わせたものよりも常に大きく、世界の勢力均衡を連合国側に決定的に有利なものとした。自由民主義諸国が有した資源の総量は、前記の理由と共に、先進的経済のために敵国側よりも大きかった (しかし、前述のとおり経済はドイツの方が優れていた)。自由民主主義の勝利は一九一四年にも 1939 年にも明らかであったわけでは決してないが、1945 年の時点ではより確実であったであろう。しかし、自由民主主義諸国を有利にしたのは、自由民主主義に内在する優位性というよりも、他でもなくアメリカの存在そのものであった。この「アメリカ要因」は、20 世紀における民主主義の勝利についての研究において広く見過ごされている点である。換言すれば、アメリカの存在がなかったとしたら、自由民主主義諸国は十中八九、20 世紀における巨大な闘争に敗北していたであろう。これは深刻な見方であり、そうした闘争の結集によって作られた世界を、直線的発展の理論やホイッグ党的な歴史観に比べ、また進歩派が我々を信じさせようとする見方に比べ、ずっと偶然に左右されやすくまたずっと弱々しいものとして我々に提示することであろう。
下 p.305
ここまで言い切ってしまうのは驚き。
しかし、支配的な見方と逆のことをいえば、民衆の扇動は指導者による「挑発」や「換作」に一方的に帰着させるべきではない。それらの指導者はそれと同程度に、強い人々の需要に応えてもいるのである。需要は供給する人間がいて満たされる。慎重で平和志向の指導者かいたとしても、民衆が自分たちの勢いで彼らを押し流してしまうことはしばしばあるし、その傾向は自由主義・民主主義の国ではさらに強まる。自由主義国イギリスをクリミア戦争 (1854~56 年) に参加させたのは主に民衆の圧力であった。熱狂的な愛国主義を掲げて好戦的な大衆の熱狂を示す「ジンゴイズム」という言葉自体、民主化が進展しつつあった 19 世紀末という時代のイギリスで流布したのである。ボーア戦争〔南アフリカ戦争〕(1899~1910 年) の間もジンゴイズムは広範に見られた。もう一つの指導的な自由民主主義国であったアメリカも、大衆の熱意に政府が事実上押し込まれるかたちでまさに同じ時期 (1898 年)、スペインとの戦争に引き込まれている。これら二つの事例で敵となった国家は自由民主主義国の要件を満たさなかったではないかという反論があるかもしれないので付言するが、ファショダ危機 (1989 年) の間、イギリスとフランスにおいて最も好戦的で最も愛国主義に熱狂し、相手に対して最も非同情的であったのは両国の世論であった。戦争から手を引いたのは、両国の政治家の方であった。研究で分かってきたことは、態度の変化を見ることができるのは、20 世紀の民主主義先進国に限定されるということである。そこでの世論は戦争に対しはるかに忌避的となった。だが同じ世紀でも新興の民主主義国は、民主主義が確立した国よりも紛争に資するような態度をとることが依然としてあるのである。
下 p.327-328
戦前の日本、少なくとも日清戦争前と、ポーツマス条約締結後に、小村邸を襲撃した者たちは同じ。
関係にも影響を与えている点であった。『自由民主主義諸国が抑制的であることの一つの側面としては、予防戦争を避ける傾向があるという点である。歴史的にいえば、脅威にさらされ、軍事的優位を保ってはいるが失いかけているという状況ですら、彼らは戦争を始めるという選択をしなかった `アメリカがまだ核の独占を保っている時に、敵対的であったソ達に対して戦争を仕掛けることを回避したという点は既に触れたが、このバターンは 20 世紀のさらに早い時期にも確認することができる。
下 p.362
戦後アメリカは、もっとも好戦的な国であることを考えると、説得力が落ちる。